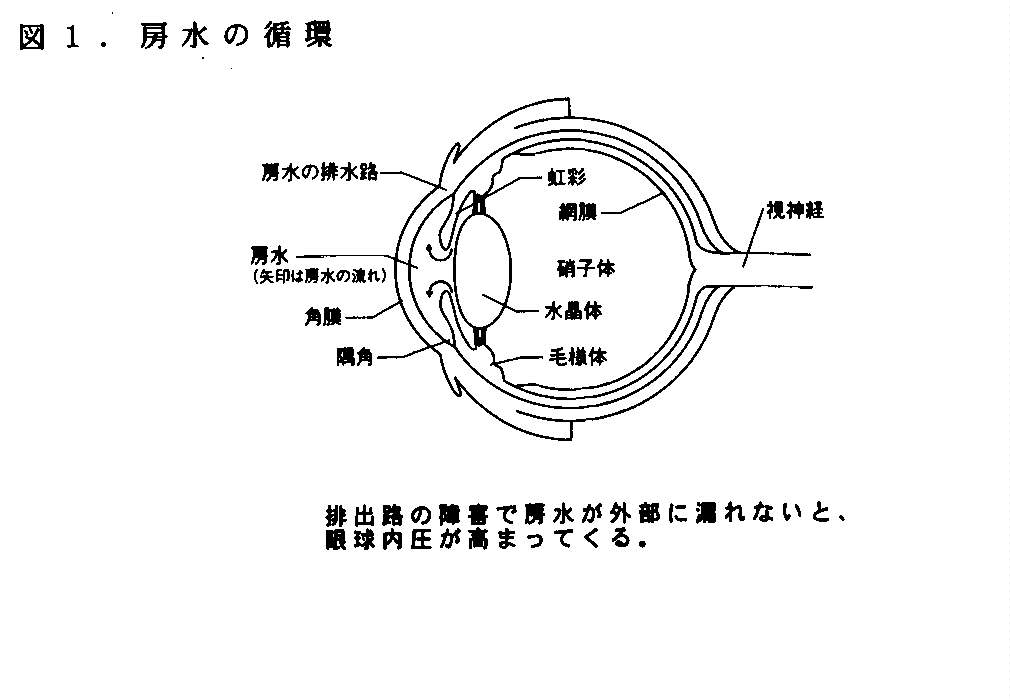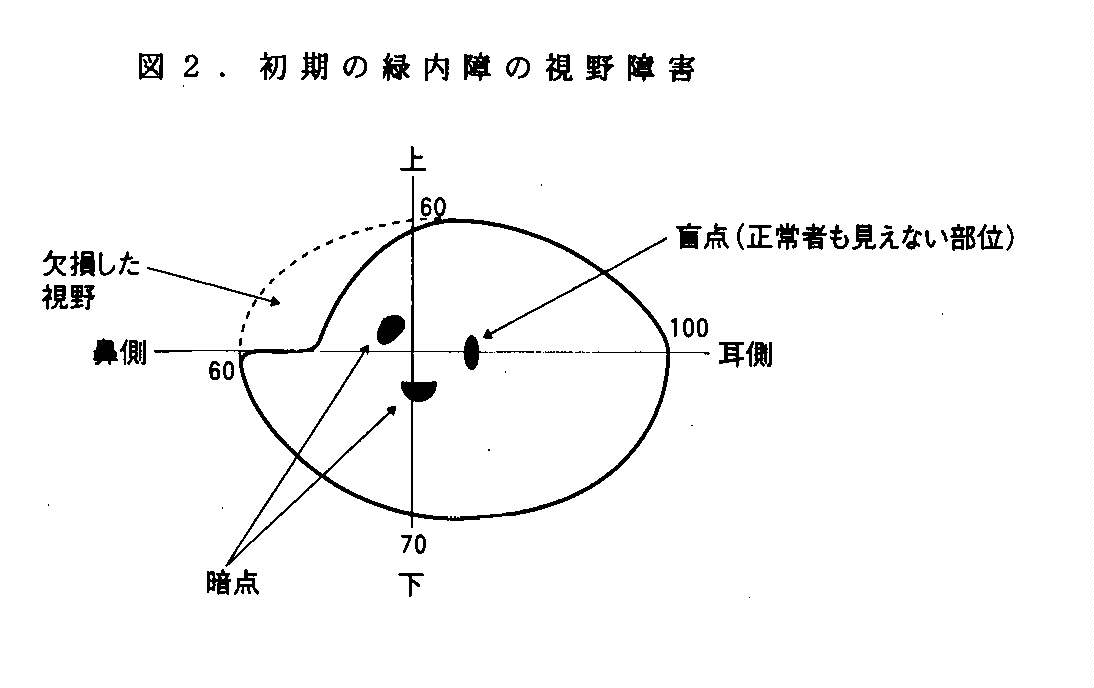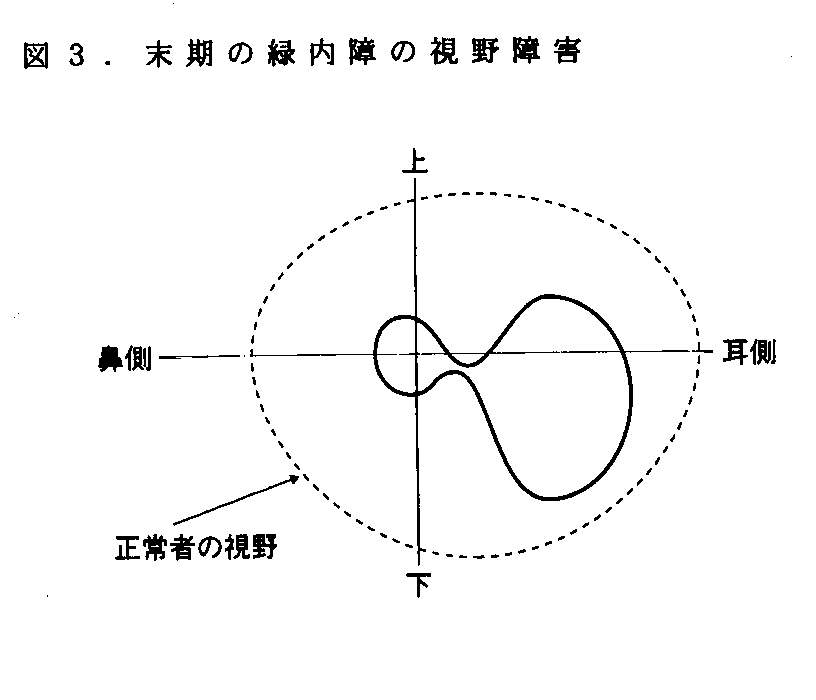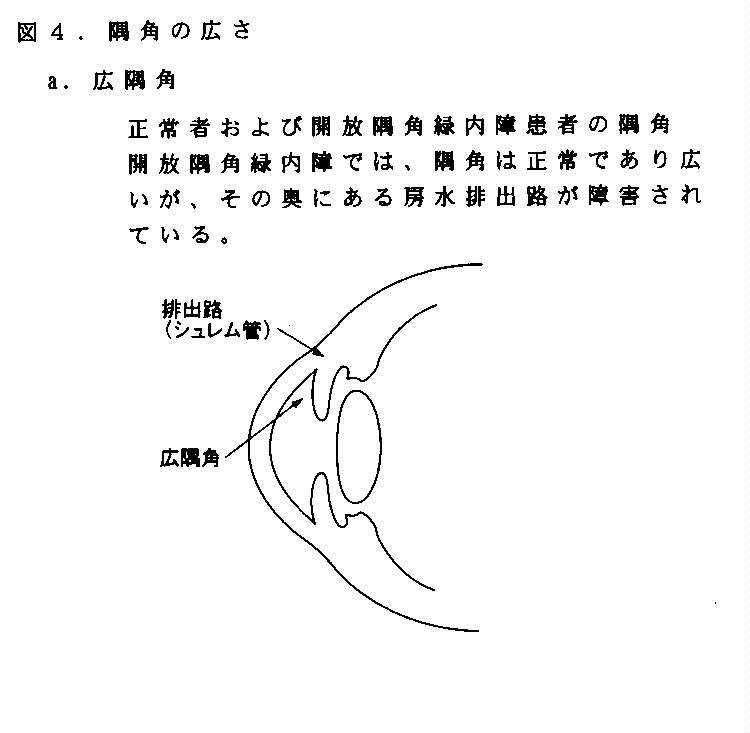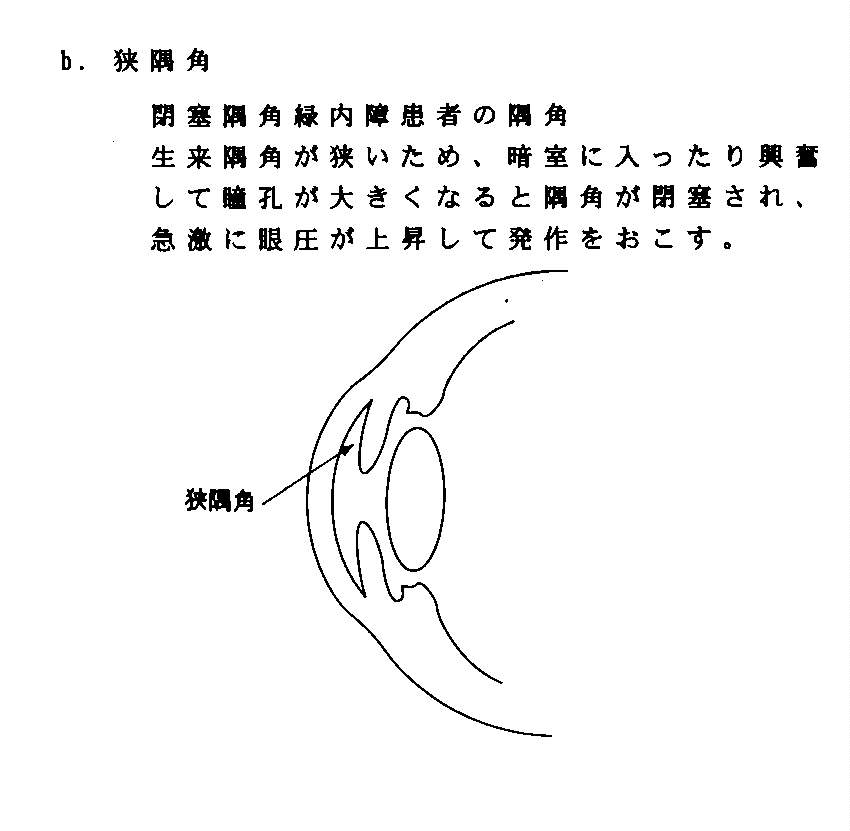角膜や水晶体などの透明な組織は、房水という透明な液体が循環することによって栄養が与えられています。この房水は毛様体で産生されて、後房から瞳孔を通って前房に入り、隅角から静脈に吸収される(図1)という循環をしているのです。 眼球の前眼部(前側の部分)を満たしている房水は、眼球を球形に保つための圧力すなわち眼圧をつくっており、この眼圧は房水や血液の循環動態によって影響を受けて変化しています。房水が眼内に産生される量と排出される量がつりあっていれば、眼圧は正常に保たれることになります。
3.健常眼圧とは
多数の人を測定した結果から、眼圧の正常値は10~20mmHgであるとされていますが、眼圧がこの正常値を越えた21mmHg以上でも眼に何の障害もない人(高眼圧症)もいれば、20mmHg以下でも障害が出てくる人(正常眼圧緑内障)がいます。 すなわち、眼を健康に保つ眼圧は個人によって異なっているのです。 そこで、その人の眼を健康に保つことができる眼圧を健常眼圧とよんでおり、各個人によって違いがあります。 何らかの原因で房水の排出路が障害されたり産生が過剰になると、眼圧が上昇し、その人の健常眼圧を越えると、視神経が圧迫されたり血流が障害されて視神経が侵され、視野が狭くなるなどの障害が生じてくると考えられています。